お知らせ
ゼロエミッションとは
2025/09/19
ゼロエミッションがなぜ今必要か
近年、気候変動や異常気象の影響が日本国内外で身近な問題になっています。温室効果ガスの排出が気候を悪化させる一方で、社会や環境、経済への損失も無視できません。こうした中で、「ゼロエミッション(Zero Emission:排出ゼロ)」という言葉が、企業や自治体の新たな標準となりつつあります。
ゼロエミッションとは、あらゆる活動から排出される温室効果ガスを、減らす努力を積み重ね、最終的には「実質的にゼロ」に近づけることを意味します。これは理念だけで終わるものではなく、数値で見える成果を上げることが期待されている取り組みです。
この記事では、「ゼロエミッションとは何か」を理解し、会社でどのように取り組めるかを具体的に学ぶことを目指します。
ゼロエミッションのはじまり
ゼロエミッションという概念が注目されるようになったのは、1994年に国連大学が提唱した「ゼロエミッション構想」が始まりです。この構想では、「廃棄物を一切出さない社会の実現」を目指し、企業や地域社会が出す廃棄物を他の産業の原料として再利用するという考え方が示されました。これは、現在よく知られている「循環型社会」の基本となる発想でもあります。
その後、2000年代に入り、地球温暖化や気候変動への対応が世界的な課題となったことで、ゼロエミッションという言葉は、廃棄物だけでなく、二酸化炭素など温室効果ガスの排出を実質的にゼロにするという意味でも使われるようになりました。
特に2015年のパリ協定をきっかけに、世界中の国や企業が「温室効果ガスの排出をゼロに近づけること」を目標に掲げるようになり、ゼロエミッションという考え方が一気に広がりました。
このように、ゼロエミッションは時代とともに意味を広げながら、今では環境だけでなく経済や社会の持続可能性を考えるうえで欠かせないキーワードの一つとなっています。
ゼロエミッションの基本の定義
ゼロエミッション(Zero Emission)事業活動などで排出される温室効果ガス(主にCO₂など)を可能な限り削減し、残る排出量についてはカーボンオフセット(植林などで吸収する方法)や代替技術で相殺することで「実質ゼロ」にする考え方です。
カーボンニュートラルとの違い
類似する概念ですが、「カーボンニュートラル」は二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスに限定した概念です。簡単に言えば、「排出した温室効果ガスの量を、吸収や削減によって相殺(=ニュートラルに)し、実質的にゼロにする」ことを意味します。
スコープ1・2・3の考え方
モノがつくられ廃棄されるまでのサプライチェーンにおけるGHG排出量(二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)などの温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gas)の排出量)の捉え方です。
・スコープ1:会社が直接コントロールできる排出(例:工場で燃料を燃やすなど)
・スコープ2:購入した電力や熱など、間接的に発生する排出
・スコープ3:サプライチェーン全体で発生する排出(仕入れ先、廃棄物、輸送など含む)
これらを把握することが、どこから手をつけるかを決めるうえでの第一歩です。
なぜ企業がゼロエミッションに取り組むべきか — メリットと背景
規制・政策の枠組み
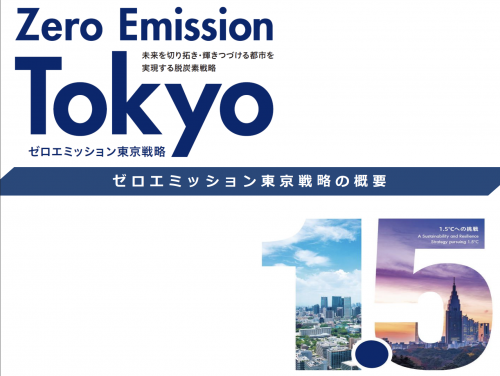
たとえば、東京都の取り組みを例にしてみましょう。「ゼロエミッション東京戦略」は、2019年5月に発表され、2050年までにCO₂排出実質ゼロを目指す都市戦略が描かれています。添付させていただいているリンク先のPDF資料は、概念理解のために参考になります。(参考PDF:ゼロエミッション東京)
改訂された戦略「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」では、2035年までに2000年比で温室効果ガス排出量を60%以上削減する新目標が設定され、具体的な施策(太陽光パネル設置義務化など)が含まれています。
こうした政府・自治体の政策は、企業にも影響を及ぼします。規制遵守だけでなく、許認可・補助金・公的評価にも関わってくるため、早めの対応がリスク低減につながります。
社会・消費者からの評価
消費者や取引先、投資家は、環境に配慮している企業を支持する傾向が強まっています。ESG投資の拡大により、「環境への責任を果たす企業」が市場評価で有利になる時代です。コスト削減・経営効率の向上
エネルギー効率の改善、再生可能エネルギーの導入、廃棄物の削減などは、初期投資が必要であっても、長期的にはコストを抑える手段となります。
ゼロエミッション実践の動き
具体的な成功例を知ることで、取り組みのイメージがわきやすくなります。- 積水ハウスグループ:新築施工現場で発生する廃棄物を27種類に分別し、さらに60種類へ拡大し、社外リサイクル業者・自社での処理を強化。これにより1棟あたりの廃棄物発生量を過去5年間で約40%削減しました。
- アサヒビール:工場で発生する副産物・廃棄物(汚泥、スクリーンかす、ガラスのくずなど)を再資源化。すべての工場で「廃棄物再資源化率100%」を達成しています。
- 日本製鉄株式会社:製鉄工程で出る副生成ガスを加熱用燃料として有効活用し、また冷却・洗浄などに使われる水の90%を再利用。さらに副産物の再資源化率が99%という非常に高い数値を実現しています。
会社でできるゼロエミッションのステップ
以下のステップで進めると、組織でも取り組みやすくなります。①現場の把握
スコープ1〜3において、どの部分で排出が多いかを調べる。電気・燃料・廃棄物などのデータを部署別に集める。
②目標設定
短期(1〜3年)、中期(5年)、長期(10年以上)で削減目標を作る。たとえば「○年までに電力使用を○%削減」など。
③小さな実践からはじめる
ペーパーレス・LED照明・省エネ機器の導入など、投資小・効果が見えるものから着手。
④従業員の巻き込み
社内でチームを作る。アイデアを出し合う。教育・研修の実施。成功した取り組みを社内共有。
⑤技術・政策を活用する
自治体の補助金・支援制度を把握。再生可能エネルギーや水素など新しいエネルギー資源の活用を検討。東京都の技術開発支援事業なども参考に。
課題と乗り越え方
ゼロエミッションを進める上で、障壁となるものもあります。- 初期コストの高さ:設備投資や技術導入には資金が必要
- 既存インフラとのすり合わせ:古い建物や設備が対応していない場合、改修が必要
- 意識と文化の変化:従業員が協力しない/変更に抵抗があると進みにくい
ゼロエミッションの上手な取り組み方
以下は、組織で効率よく進めるための工夫です。・成果が見える指標(KPI)を設け、定期的にレビュー
・投資回収期間を考慮した設備投資を行う(ROIの見込みを把握する)
・社内外のステークホルダー(取引先、地域、消費者など)に情報を開示し、協力を呼びかける
・新しい技術を試験導入し、小さな実証実験から経験を積む
・政策・補助金・助成制度を活用することでコストや負担を軽減する
まとめ:未来を築く選択としてのゼロエミッション
ゼロエミッションへの取り組みは、単なる「環境対策」ではなく、企業価値を高める戦略的選択です。社会的信頼の構築、従業員の意識向上、そして未来世代への責任ある姿勢の表れでもあります。サステナブルな経営は今や“選ばれる企業”の条件となりつつあります。脱炭素社会への移行は、決して一夜にして達成できるものではありません。しかし、少しずつでも行動を重ねることで、確実に変化は起こせます。
あなたの会社が次の一歩を踏み出すことで、業界全体、地域社会、そして地球に大きな影響を与えることができるのです。今こそ、ゼロエミッションという未来への投資を、確かな行動として始めましょう。


